ファシリテーターの言い換え語のおすすめは?ビジネスやカジュアルに使える類義語のまとめ!
本記事では、ファシリテーターの言い換え語・同義語(類義語)を解説します。
- ビジネスで使えるきっちりした類語
- 友達同士でカジュアルで使える類語
に分けていくつかのアイデアをまとめました。
また、カタカナ・英語でかっこよく言い換えたい場合のワードもいくつか紹介します。
実際に使われているワードばかりです。ぜひ参考にしてください。
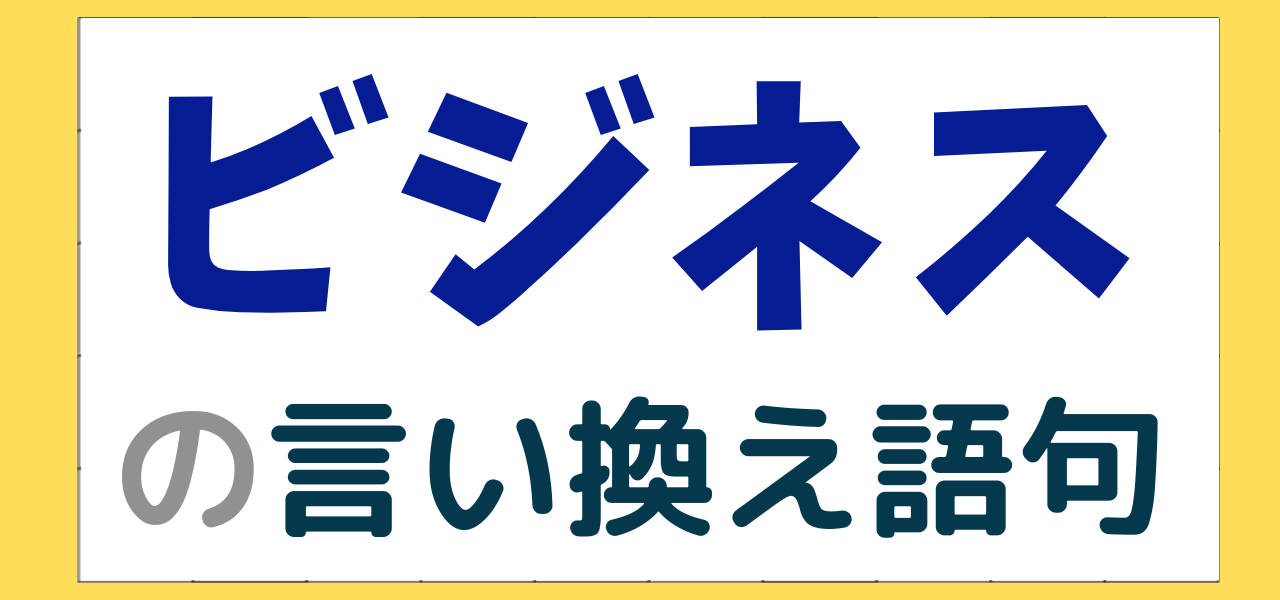 →ビジネスの言い換えを見る | 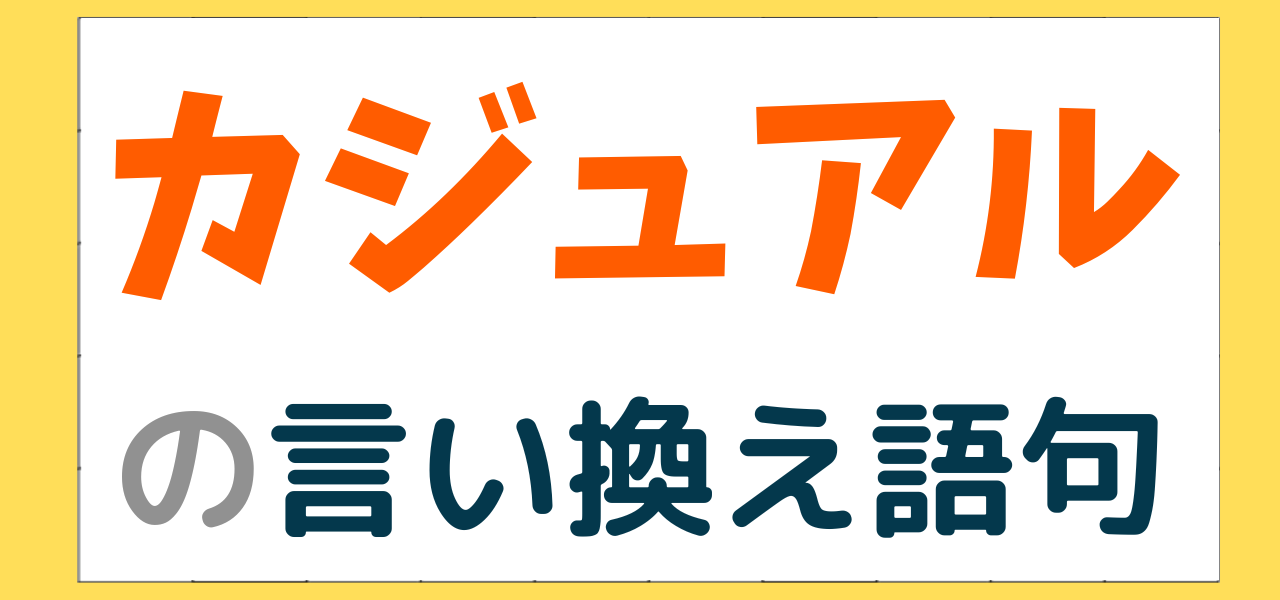 →カジュアルの言い換えを見る | 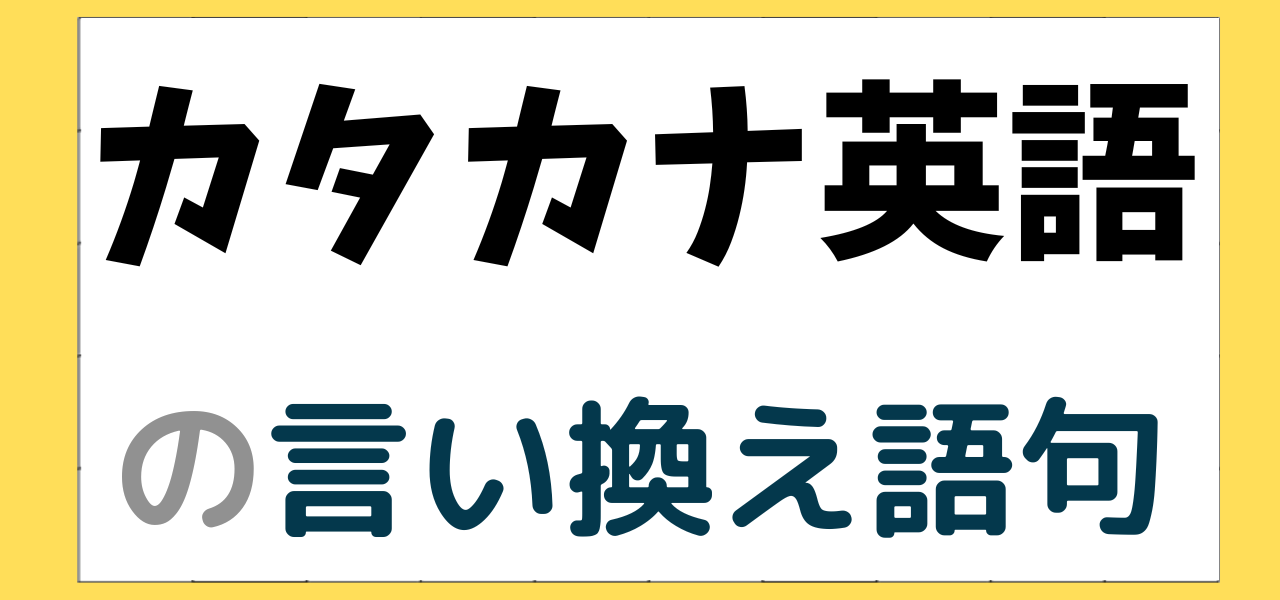 →英語・カタカナの言い換えを見る |
ファシリテーターとは? そもそもどんな意味か?
まずはファシリテーターとはどんな意味なのかをおさらいします。
すでに意味をご存知の方は、次の項目まで飛ばしていただき大丈夫です。
意味
まず意味は以下のとおりです。
参加者を手助けし導いて共にゴールに向かい進んでいくリーダーのような役割
—
会議や商談などで中立的な立場に立った上で会議中に発せられた意見をまとめ、より良い結論に導く役割を担う人
—
グループや組織がより協力し、共通の目的を理解し、目的達成のための計画立案を支援する人のことである。
意味を全て見る
- 意見や考えを公平に扱い、結論を誘導しない中立的な立場にある人物です。
- 複数の人や物事を繋ぐ役割をする人のこと。
- プロジェクトや会議などの集団活動がスムーズに進むように支援する役割
例文
つづいて、ファシリテーターを用いた例文を紹介します。
今日の講座は目標設定の効果的な手法についてです。この講座のファシリテーターは〇〇さんです。
PMOとして、システムの開発会議のファシリテーターの役割を担っています。
例文を全て見る
- 彼はファシリテーターとしてその会議に出席していたが、自分の意見を言いたくてしかたなかった。
- 会社員として長年働かせている私は、その社内の会議のファシリテーターを引き受けた。
- ファシリテーターに向いていると思う人は、常に冷静で感情的にならず、中立的な立場で物事を考えられる人だと思う。
- 地域の住民と行政の意見、討論の場としての公聴会で、ファシリテーターの役割は、住民の意見を公平にすくいあげ、行政との意思疎通を促進させ、一定の結論を導き出す手助けをします。
- この案件に関して皆の意見が割れてしまって、なかなかまとまらなかったのですが、ファシリテーターの采配がとても良かったので話が上手く進みました。
- これまでなかなかまとまらなかった会議を、彼女がファシリテーター役を担ってくれたおかげで、スムーズにまとまって感謝している。
- ファシリテーターは、参加者の意見を引き出すことが重要です。そのためには、参加者の意見に耳を傾け、質問や肯定的なフィードバックを行うなど、参加者が安心して発言できる環境を整えることが大切です。
注意点(違和感のある、または失礼な使い方)
この言葉を使ううえでの注意点は以下のとおりです。違和感のある使い方にならぬよう注意しましょう。
座学の講師には使わない。あくまでワークショップ形式やアクティビティがある講座における講師としての呼び名がファシリテーター。
—
動詞ではなく名詞であり、とある立場の人を指している点です。
—
主に議論の場で活躍し、議事進行やセッティングを担当します。しかし、自分自身が会議や議論の最中に自分の意見を述べたり、意思決定をすることはありません。
注意点を全て見る
- 会議などの参加者たちの考えをまとめる立場であり、会議を進行していく「司会」と混同しないように注意する。
- 単に会を進行する司会役ではなく、内容を熟知した上で有意義に進行させる役どころであることを認知して使いたい言葉です。
- 話し合っている双方の目的をよく理解している人でなければ使わない。
- 会議の進行を円滑にするために、参加者の意見を尊重し、公平に議論を進めることが求められます。そのため、ファシリテーターは、会議の議題や参加者の意見に対して、自分の意見や主張を述べないように注意する必要があります。
ビジネスで使える丁寧なファシリテーターの言い換え語のおすすめ
ビジネスで使えるフォーマルな言い換え語を紹介します。
それぞれ見ていきます。
橋渡し役
まずは、橋渡し役です。
意味やニュアンスの違いは以下のとおり。
「橋渡し役」は双方の間を取り持つ役目を担うニュアンス。二者以上を繋げる場合に「君が橋渡し役に適任だと思う」というような使い方をするのがおすすめ。
パイプ役
2つ目は、パイプ役です。
意味やニュアンスの違いは以下のとおり。
「交渉のパイプ役になった。」などといった、二者の間をとりもつ人や組織、などの表現に使用することがおすすめです。
つなぎ役
3つ目は、つなぎ役です。
意味やニュアンスの違いは以下のとおり。
「つなぎ役」は、間に入って中立な立場で両者を仲介する人や物を指します。「ファシリテーター」は、グループや個人の間のコミュニケーションやプロセスを効果的に進行させるためのサポートや仲介をする役割を持つ人を指します。
懸け橋
4つ目は、懸け橋です。
意味やニュアンスの違いは以下のとおり。
「両国親善の懸け橋となることになった。」などといった、橋渡し、なかだち、などの表現に使用することがおすすめです。
仲介役
5つ目は、仲介役です。
意味やニュアンスの違いは以下のとおり。
双方の中に立ってその便宜をはかることを指す。「私が仲介役を担うことになりました」というような使い方をするのがおすすめ。
アドバイザー
6つ目は、アドバイザーです。
意味やニュアンスの違いは以下のとおり。
ファシリテーターが何かを主体的に動かすのに対し、アドバイザーは適宜サポートに入るニュアンスの違いがある。
メンター
7つ目は、メンターです。
意味やニュアンスの違いは以下のとおり。
ファシリテーターが一対一より一対複数な印象に対し、メンターは一対一のニュアンスが強い。講座ではなく個人トレーニングに使う。
ファシリテーターのカジュアルな言い換え語のおすすめ
友達同士で使えるようなカジュアルな言い換え語のおすすめを紹介します。
つなぎ役
まずは、つなぎ役です。
意味やニュアンスの違いは以下のとおり。
人や組織の間に立って、両者を仲介する役割を持った人や物のことを意味する。A社とB社の間に入って、双方の言い分などを伝える役割を担う人に対して使う。
取り持ち
カジュアルの2つ目は、取り持ちです。
意味やニュアンスの違いは以下のとおり。
「意中の人との取り持ちを頼む。」などといった、両者の間に立って仲を取り持つこと、仲立ちをすること。また、その人などの表現に使用することがおすすめです。
橋渡し役
つづいて、橋渡し役です。
意味やニュアンスの違いは以下のとおり。
2つの異なる側やグループ間でのコミュニケーションや調整を助ける役割を持つ人や要素を指します。こちらも、関係を円滑にするための仲介者やサポート役を意味します。
口きき
4つ目は、口ききです。
意味やニュアンスの違いは以下のとおり。
複数の間を取り持つ様子ですが、ちょっと俗っぽい言い方です。少し秘密めいた印象もするので親しい同士で使った方がいいです。
架け橋
5つ目は、架け橋です。
意味やニュアンスの違いは以下のとおり。
2つの異なるグループ、考え、または状況間のつながりやコミュニケーションを助ける存在や要素を指します。
仲人
6つ目は、仲人です。
意味やニュアンスの違いは以下のとおり。
ファシリテーターは意見や考えを公平に扱い、結論を誘導しない中立的な立場にある人物で、仲人とは結婚の仲立ち役として夫婦の出会いを設け、結婚のまとめ役として結納、結婚式の仲立ちをする人物です。日本の古い家族制度の名残りであり家と家の結婚という考え方から生まれた結婚のフィクサー的な役割をする人を表現する場合に、おすすめの言葉です。
キューピッド
7つ目は、キューピッドです。
意味やニュアンスの違いは以下のとおり。
恋愛の成就を思わせる言葉ですが、敢えて恋愛以外の事にもいたずらっぽく使うことが出来ます。揶揄している表現なので親しい間同士で使う言葉です。
仲を取り持つ
8つ目は、仲を取り持つです。
意味やニュアンスの違いは以下のとおり。
「仲を取り持つ」は人と人の間柄が良好な関係となるよう、双方の間に入って世話することを指す。「二人の仲を取り持つことができるのはあなただけなんじゃない?」というような使い方をするのがおすすめ。
進行役
9つ目は、進行役です。
意味やニュアンスの違いは以下のとおり。
とある会議の目的を達成するための進行役はその名の通り進行するのがゴールであるが、ときにファシリテーターは、会議のゴールの導く責務がある。
ファシリテーターの横文字・カタカナ英語の言い換え語のおすすめ
最後は横文字・カタカナ英語での言い換え語を紹介します。
こちらはリストのみとなります。
- パイプ
- コーディネーター
- フィクサー
- facilitator
- coordinator
- fixer
- instructor
かっこよく表現したい際、参考にしてください。
まとめ
以上がファシリテーターの言い換え語のおすすめでした。
さまざまな言葉があることがわかりますね。
基本的な意味は同じでも微妙にニュアンスが違ったりもするため、TPOに合わせて言い換え語を使い分けていきましょう。
振り返り用リンク↓
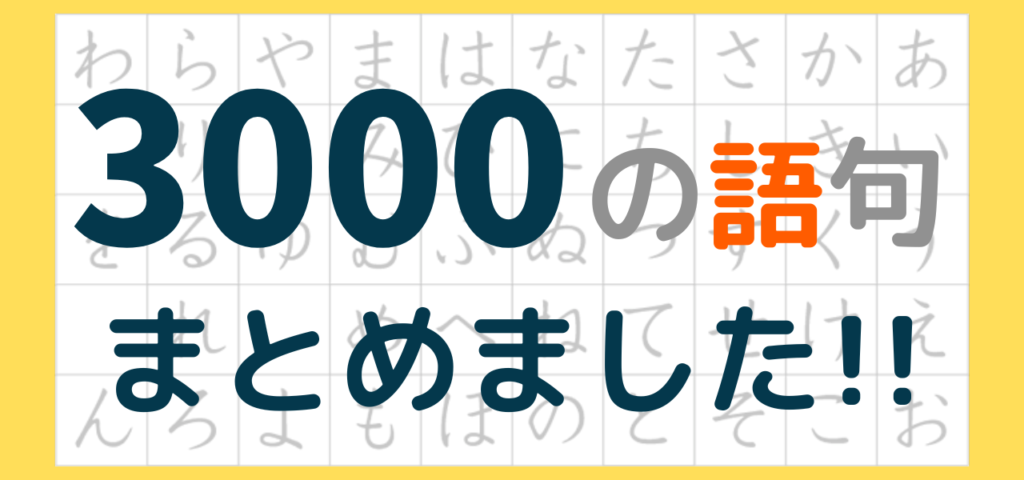
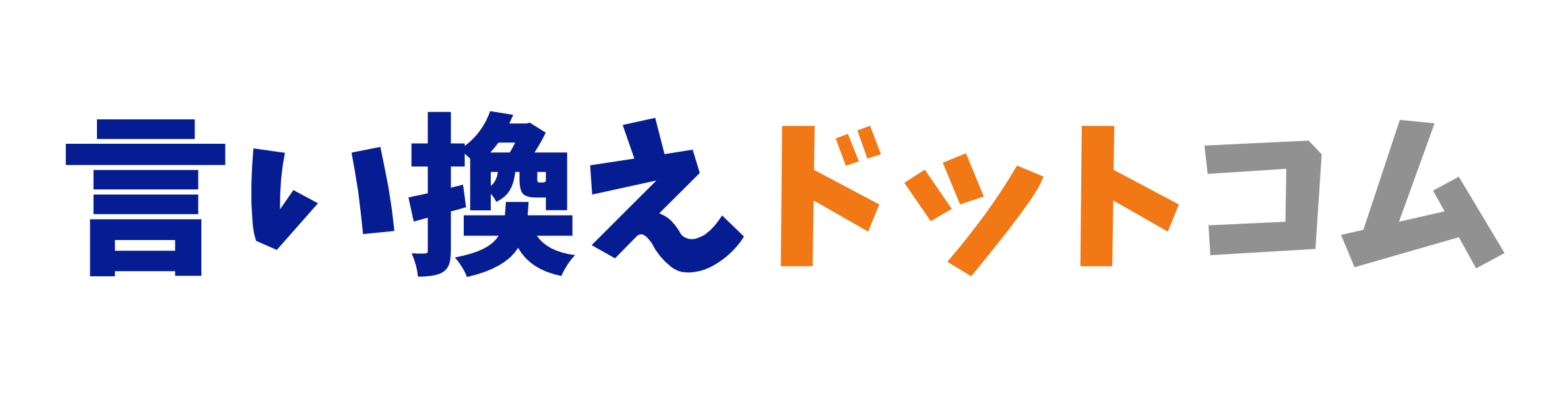

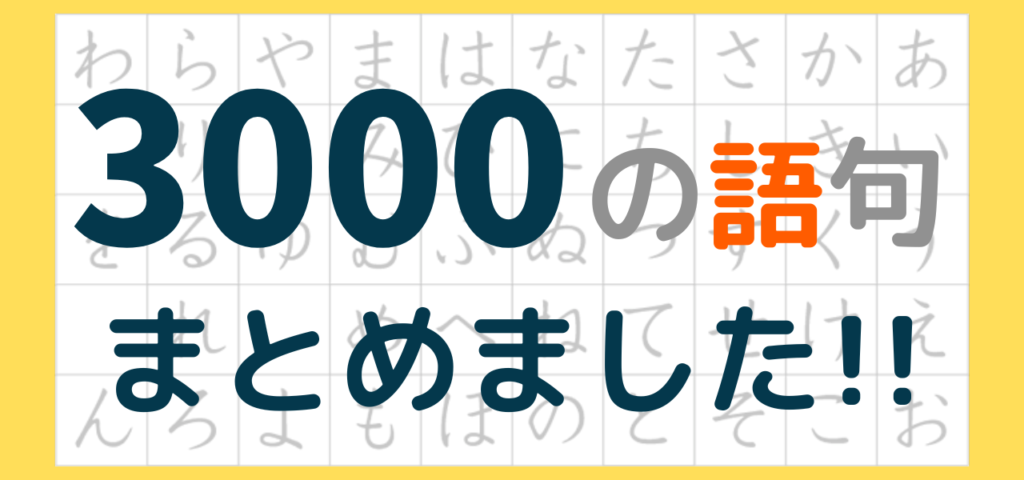
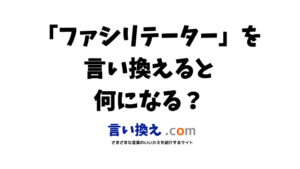
コメント