本稿の言い換え語のおすすめは?ビジネスやカジュアルに使える類義語のまとめ!
本記事では、本稿の言い換え語・同義語(類義語)を解説します。
- ビジネスで使えるきっちりした類語
- 友達同士でカジュアルで使える類語
に分けていくつかのアイデアをまとめました。
また、カタカナ・英語でかっこよく言い換えたい場合のワードもいくつか紹介します。
実際に使われているワードばかりです。ぜひ参考にしてください。
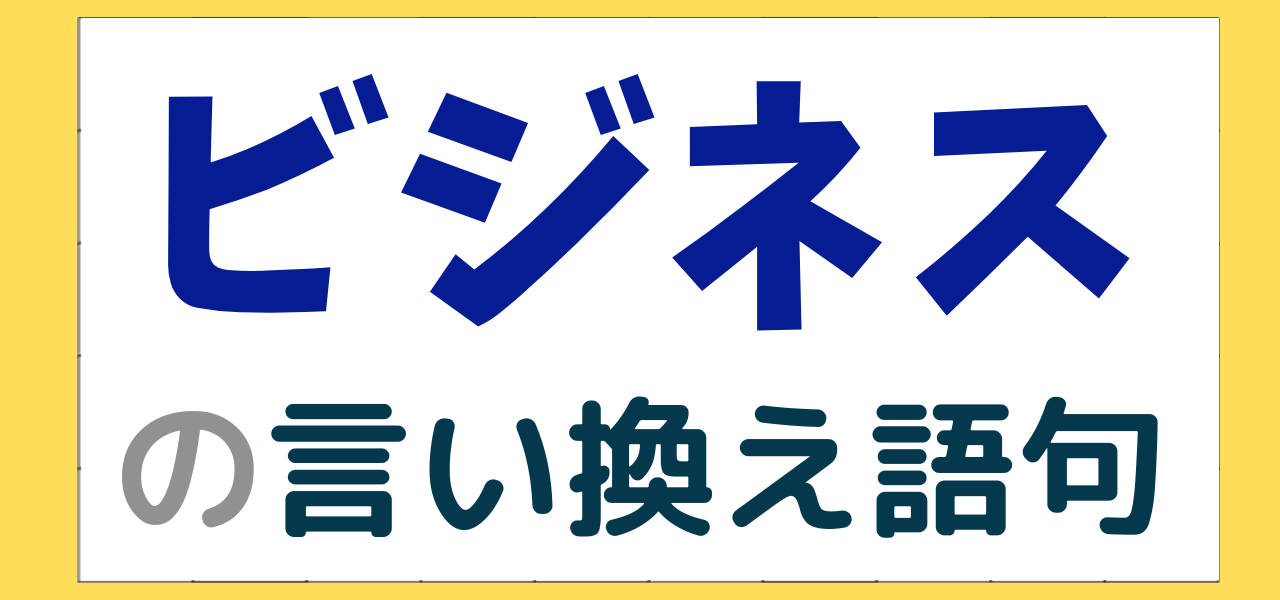 →ビジネスの言い換えを見る | 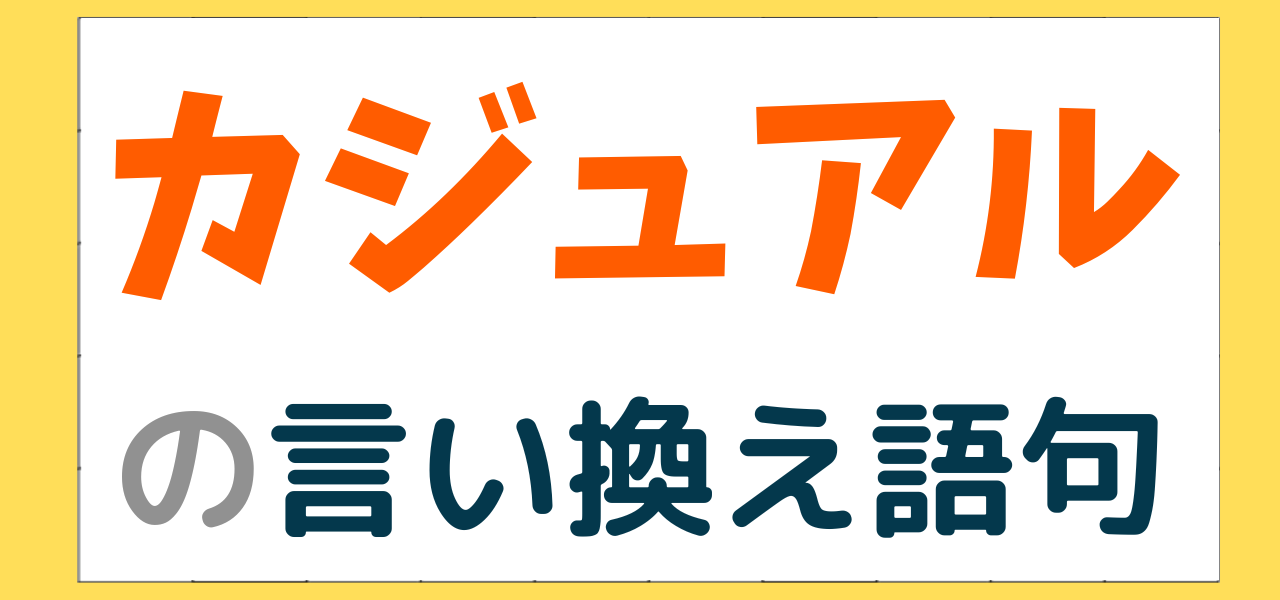 →カジュアルの言い換えを見る | 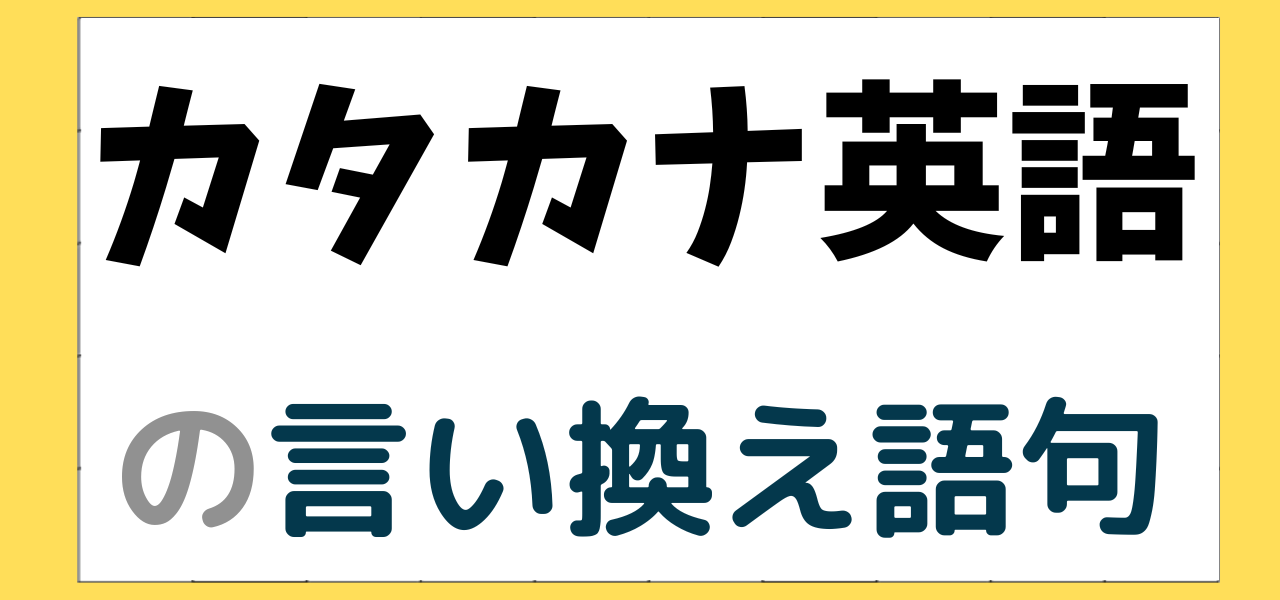 →英語・カタカナの言い換えを見る |
本稿とは? そもそもどんな意味か?
まずは本稿とはどんな意味なのかをおさらいします。
すでに意味をご存知の方は、次の項目まで飛ばしていただき大丈夫です。
意味
まず意味は以下のとおりです。
この書籍やこの論文などの意味で書いた本人が使う。
—
もとになる原稿や、話題にしていること、この原稿という意味です。
—
今、話題にしている、もしくは手元にある原稿。
意味を全て見る
- 論ずる側が原稿について示す時に用いる言葉です
- 論文や書物などでその書籍自体を指すことを意味する。
例文
つづいて、本稿を用いた例文を紹介します。
本稿では、特に日本の文化について研究した結果を記しています。
本稿の著者は、10年もの歳月をかけて調べてきた、とある村の伝承について書いている。
例文を全て見る
- 校正作業にあたり、先ずは本稿に関する誤記や表記ゆれなどを洗い出してください。
- 本稿のテーマは、広い視点で言えば、昨今話題のSDGsに関係していると言えます。
- 前回の会議で指摘があった部分を、本稿では次のように修正しております。
- 平均的男性とは、本稿では年収が200万円から500万円までの成人男性のことだと定義する。
- 本稿の内容を理解するためには、関連する文献を読む必要があります。
- それでは、本稿につきましては導入部分となりますので、気軽に聞いてください
注意点(違和感のある、または失礼な使い方)
この言葉を使ううえでの注意点は以下のとおりです。違和感のある使い方にならぬよう注意しましょう。
論文や書籍などによく使われるため、短い文章に使うと違和感がある。
—
かなり改まった言い方なので、論文発表などのシーン以外の場面で用いると、違和感があるかもしれません。
—
聞き手や読む人といった相手に、「この原稿」「この文書」という表現で、共通の一つのものが認識される状況で使わなければならない。
注意点を全て見る
- 基本的に書類や書物の内部で使う言葉であり、会話などで使うことはない。
- 本稿という言葉は、カジュアルな場面ではあまり使いません。ビジネスでよく使われるため、相手もその言葉を知っている必要があります。
- かなりかしこまった言い回しのため、内容によってやさしい言葉に置き換えることも必要です
ビジネスで使える丁寧な本稿の言い換え語のおすすめ
ビジネスで使えるフォーマルな言い換え語を紹介します。
それぞれ見ていきます。
本論文
まずは、本論文です。
意味やニュアンスの違いは以下のとおり。
本稿は、論文や書籍などの作家が最初にこの書籍に何が着れているのかを記すときに使う。本論文は、論文に限られる。
元の原稿
2つ目は、元の原稿です。
意味やニュアンスの違いは以下のとおり。
助詞が入っていることで、聞き手にも分かりやすく伝えることができる。本稿には同音異義語があるため、時に伝わりづらいと考えられる。
今回の原稿
3つ目は、今回の原稿です。
意味やニュアンスの違いは以下のとおり。
元のワードに比べて、例えば何度も修正を重ねた原稿であれば、時系列で一番新しいものというニュアンスになるので、一つ前の原稿が議題に上がっていた場合は使えない。
当稿
4つ目は、当稿です。
意味やニュアンスの違いは以下のとおり。
漢字を見ると比較的意味が伝わりやすいが、耳で聞いただけだと同音異義語が多く、伝わりにくい可能性がある。
本書
5つ目は、本書です。
意味やニュアンスの違いは以下のとおり。
該当する書物について表した言葉です。多少、敷居の高い雰囲気のある言葉のため、あらたまった場面には適しています
本著
6つ目は、本著です。
意味やニュアンスの違いは以下のとおり。
元のワードは「原稿」を連想させ、言い換え語は「著書」「本の形になっているもの」を連想させるところが、違いです。社内での会話におすすめです。
本論
7つ目は、本論です。
意味やニュアンスの違いは以下のとおり。
この論やこの論文・議論という部分が違います。原稿ではなく、論文や議論について中心的なことを説明するときにおすすめです。
本論考
8つ目は、本論考です。
意味やニュアンスの違いは以下のとおり。
この文章について論じて考える部分が違います。あるテーマについて論じたり、考究した文章を紹介するときにおすすめです。
本稿のカジュアルな言い換え語のおすすめ
友達同士で使えるようなカジュアルな言い換え語のおすすめを紹介します。
小論
まずは、小論です。
意味やニュアンスの違いは以下のとおり。
本稿は書籍などの作家が最初に書くニュアンスで、小論は作家が自分の書いた文章をへりくだっていうニュアンスになる。
お手元の原稿
カジュアルの2つ目は、お手元の原稿です。
意味やニュアンスの違いは以下のとおり。
元のワードは「お手元の原稿」を指すこともあれば、論文の中で、論文自身を指すために用いられることもありますが、言い換え語は「今、あなたたちがお手元に持っている原稿」を明確に指している点が、ニュアンスの違いです。同僚と原稿を手に議論している場合などに用いるのがおすすめです。
この話題
つづいて、この話題です。
意味やニュアンスの違いは以下のとおり。
どのような年代の人にも分かりやすく伝わる。カジュアルに聞こえることもあれば、テレビ番組などで使われることも多い。
さわり
4つ目は、さわりです。
意味やニュアンスの違いは以下のとおり。
話の山場や肝要な部分を表す言葉として用いられます。そのため、あらすじや要点など概要を示す時の方が多いです
下り
5つ目は、下りです。
意味やニュアンスの違いは以下のとおり。
話の内容や章など、項目を表した言葉です。多少の曖昧さはあるものの、万能で便利な言い回しとして活用できます
拙論
6つ目は、拙論です。
意味やニュアンスの違いは以下のとおり。
本稿は書籍などの作家が最初に書くニュアンスがある。拙論は、つたない論文というニュアンスで、書いた本人が使う。
本作
7つ目は、本作です。
意味やニュアンスの違いは以下のとおり。
おもに小説などの書籍で、その書籍自体を指す言葉である。作品というニュアンスがあり、小説にかぎらず幅広い分野で使っていける。
本書
8つ目は、本書です。
意味やニュアンスの違いは以下のとおり。
主となる文書や、添付文書・付録、 正式の文書を言う部分が違います。あるものに関しての、下書きなどではなく正式の文章であるときにおすすめです。
本文
9つ目は、本文です。
意味やニュアンスの違いは以下のとおり。
主に短い文章中でその文章自体を指す言葉で用いる。おもに国語の試験などで用いる言葉であり、一般的である。
本稿の横文字・カタカナ英語の言い換え語のおすすめ
最後は横文字・カタカナ英語での言い換え語を紹介します。
こちらはリストのみとなります。
- ディス レポート
- This topic
- This theme
- this paper
- this article
- this draft
- point of paper
- This book
- main research
- Main essay
かっこよく表現したい際、参考にしてください。
まとめ
以上が本稿の言い換え語のおすすめでした。
さまざまな言葉があることがわかりますね。
基本的な意味は同じでも微妙にニュアンスが違ったりもするため、TPOに合わせて言い換え語を使い分けていきましょう。
振り返り用リンク↓
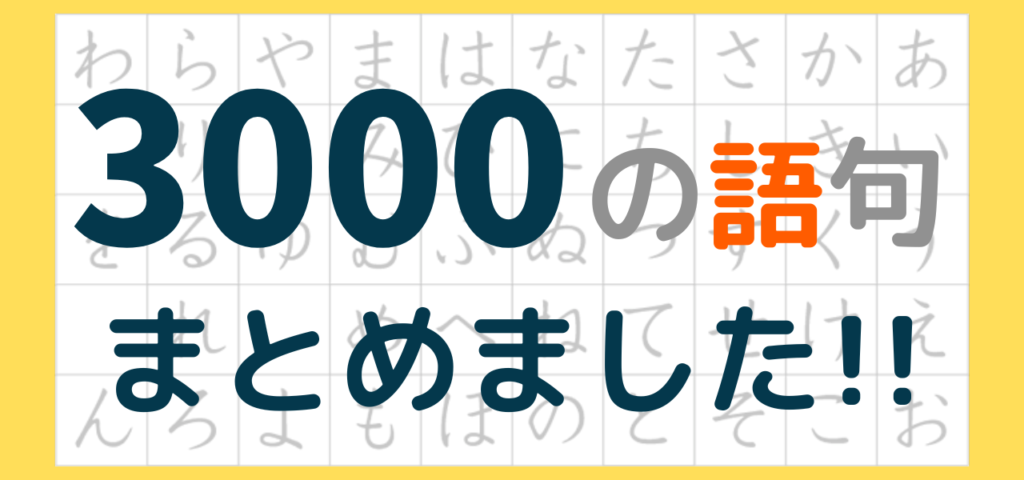
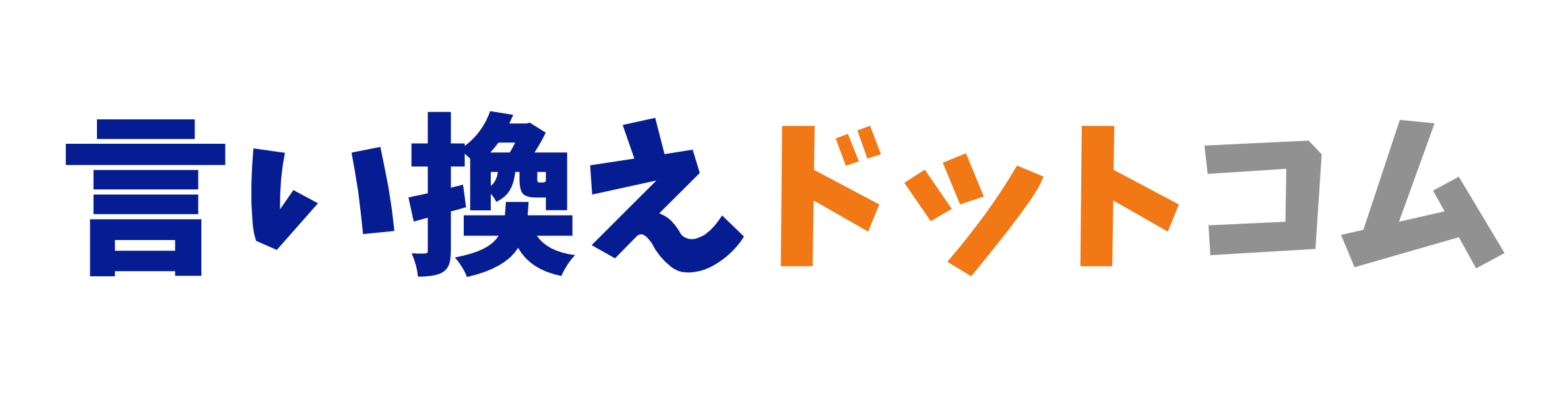

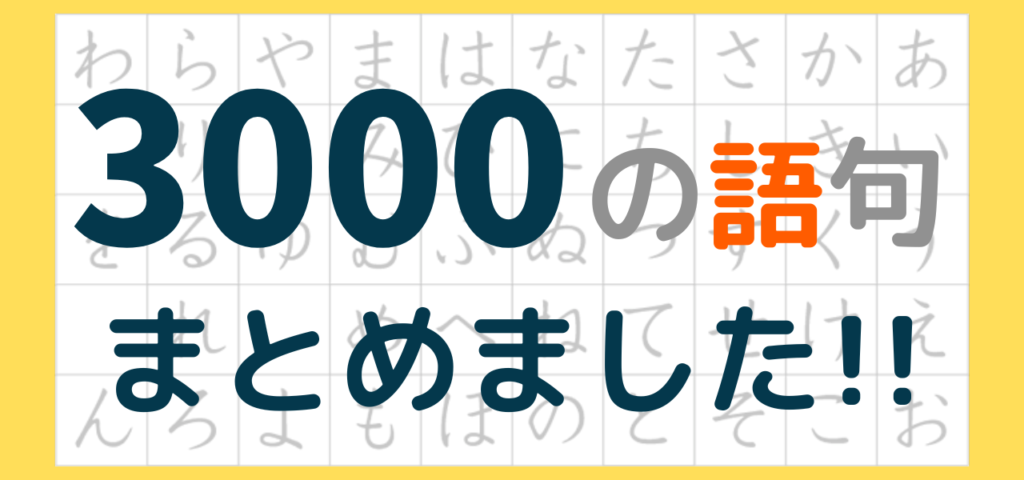
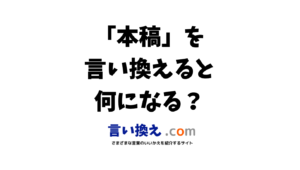
コメント