物事のし始めの言い換え語のおすすめは?ビジネスやカジュアルに使える類義語のまとめ!
本記事では、物事のし始めの言い換え語・同義語(類義語)を解説します。
- ビジネスで使えるきっちりした類語
- 友達同士でカジュアルで使える類語
に分けていくつかのアイデアをまとめました。
また、カタカナ・英語でかっこよく言い換えたい場合のワードもいくつか紹介します。
実際に使われているワードばかりです。ぜひ参考にしてください。
物事のし始めとは? そもそもどんな意味か?
まずは物事のし始めとはどんな意味なのかをおさらいします。
すでに意味をご存知の方は、次の項目まで飛ばしていただき大丈夫です。
意味
まず意味は以下のとおりです。
ものごとを開始する。 行いはじめる。
—
物事を始めたころのこと
—
きっかけや発端を表す言葉です
意味を全て見る
- 何か物事をはじめるときの最初のこと
- 諸々の物や事柄の、一番初めの段階
- 物事を行っていない状態から、行う状態にすること。
- 仕事や芸事などに着手した状態のこと。
- 新たな事象の開始を表す言葉
例文
つづいて、物事のし始めを用いた例文を紹介します。
物事のし始めはなかなか認知されないことも多いが、継続することはとても重要だ。
物事のし始めには、始めたとわかってもらうための勢いが必要なときもある。
例文を全て見る
- 物事のし始めが肝心だから、やり方をきちんと確認して、ミスの無いように気をつけよう。
- 私の所感で申し訳ないのですが、物事のし始めは大体が上手くいくことの方が少ないのです。でも、それが面白いのです。初めから上手くいったら飽きるでしょう。
- すべての物事のし始めは大事だ。物事のし始めがすべてを決める。
- 物事のし始め段階で、一番肝要なことって何でしょう?私はまず計画を立てて、準備をしっかりすることかなと思うのですが。
- 物事のし始めには、十分な事前の準備を行ったうえで、やるのが良いだろう。
- 物事のし始めには、まず必要な道具が揃っているかを確認してください。
- 物事のし始めはには、十分な準備をしたうえで、新たな気持ちの切り替えが大切です。
注意点(違和感のある、または失礼な使い方)
この言葉を使ううえでの注意点は以下のとおりです。違和感のある使い方にならぬよう注意しましょう。
開始したばかりの状況で使うことが多い。
—
言い換えの自由度が高いため、発信する側のセンスに任される言葉です
—
物事がスタートするタイミングで使うので、終盤や途中などではつかないため注意。
注意点を全て見る
- 「物事」が何を指すのか曖昧なので、具体的な言葉に置き換えると相手に伝わりやすいです。また「し始め」という言葉は、独立した一つの言葉としてはやや弱いように思われるため、よりくっきりとした輪郭の言葉に置き換えると相手もわかりやすいかと思います。
- 創立するなど、新しくつくったり、起こしたりする意味もある。
- 「し始め」の「し」は「する」の活用形だと思われるので、「し始める」の前に動詞があったほうがよい気がします(たとえば、「話し始める」)。そうなると、物事という目的語とその動詞の整合性をとらなければならないので、使い方が難しく、自信のない人はあまり使わない方がいいと思います。
- 「物事のし始めに、社長の訓示を御願いします。」という使い方は、ビジネスの世界で使うのには違和感があります。物事のし始めという言葉は、具体的に何を意味するのか、漠然としていて、公式な場面で使うには、丁寧な表現ではないと思います。この場合は、「新たな年度の始まりに当たって」とか、「新年の始業に当たって」とか表現すべきだと思います。
ビジネスで使える丁寧な物事のし始めの言い換え語のおすすめ
ビジネスで使えるフォーマルな言い換え語を紹介します。
それぞれ見ていきます。
開始
まずは、開始です。
意味やニュアンスの違いは以下のとおり。
はじまること。はじめること。交渉を開始する、試合開始、等。
しかかり
2つ目は、しかかりです。
意味やニュアンスの違いは以下のとおり。
物事の中でも特に仕事に手をつけて始めた時のことを指します。
元のワードはいろんな物事に対して幅広く使える言葉ですが、この言葉は仕事のみとかなり限定的です。
仕事で使う時におすすめで、特に製造業で使われることが多い言葉といえます。
起源
3つ目は、起源です。
意味やニュアンスの違いは以下のとおり。
物事の歴史的な起こりについて用いる。物事のおこり。もと。
初期段階
4つ目は、初期段階です。
意味やニュアンスの違いは以下のとおり。
最初に起こす行動や動作のことを指す。物事を行う時の最初の段階の時に使う。
端緒
5つ目は、端緒です。
意味やニュアンスの違いは以下のとおり。
物事の始まりや解決の糸口を表す言葉ですが、スマートで簡潔な言い換えとしてあらたまった場面でも有効な言葉です
着手
6つ目は、着手です。
意味やニュアンスの違いは以下のとおり。
元のワードと同じようなニュアンスの言葉ですが、元のワードよりも積極的に動作を行っている印象を与える言葉です。
発端
7つ目は、発端です。
意味やニュアンスの違いは以下のとおり。
こちらはどちらかと言えばよい意味で使われることの少ない言葉かもしれませんが、物事の始まるタイミングで何が起こったかをたどる場面に適切です
物事の序盤
8つ目は、物事の序盤です。
意味やニュアンスの違いは以下のとおり。
一続きの物事のはじめのころ、初期の情況という意味合いの語で、囲碁や将棋でも対局開始後すぐをさすことができるのでおすすめ。
幕開き
9つ目は、幕開きです。
意味やニュアンスの違いは以下のとおり。
「新しい年度を迎えるにあたり、新しいプロジェクトの幕開きです」という場合は、ただ、物事のし始めだけでなく、新たな始まりを強調するニュアンスがあります。
元々は歌舞伎の世界で、場面が変わって新たな幕が開くというのが語源のようで、ビジネスの場で、雰囲気を刷新する場合に使えます。
嚆矢濫觴
10個目は嚆矢濫觴です。
意味やニュアンスの違いは以下のとおり。
「今日が、いよいよ、ライバルとの戦いの嚆矢濫觴です。」という場合は、物事の始まりの中でも、戦いの始まりというニュアンスです。
もともとは、中国の故事に倣い、鏑矢を放って戦いの始まりの合図を意味するようです。メンバーの意欲を鼓舞したい場合には使える言葉です。
物事のし始めのカジュアルな言い換え語のおすすめ
友達同士で使えるようなカジュアルな言い換え語のおすすめを紹介します。
始まり
まずは、始まりです。
意味やニュアンスの違いは以下のとおり。
一般的に使われ、物事が起こるきっかけの意でも使われる。
やり始め
カジュアルの2つ目は、やり始めです。
意味やニュアンスの違いは以下のとおり。
友達や後輩、親しい相手に使えます。書き言葉というよりは、ざっくばらんに話す時に使うと良い。
最初の一歩
つづいて、最初の一歩です。
意味やニュアンスの違いは以下のとおり。
元の言葉にある起源をたどる場面で適切な言葉です。何がきっかけか、またその時の描写などが伴うとリアルさが増す言い換えです
事始め
4つ目は、事始めです。
意味やニュアンスの違いは以下のとおり。
「正月の事始めに、皆で初詣に行こう。」という使い方は、祭りごとという故事に語源があり、物事のはじめというだけでなく「神事」のニュアンスが込められています。正月や、年中行事などの区切りに使えます。
取っ掛かり
5つ目は、取っ掛かりです。
意味やニュアンスの違いは以下のとおり。
物事を始めることを指す。今から、その物事を始めるという時に使う。
序の口
6つ目は、序の口です。
意味やニュアンスの違いは以下のとおり。
「彼のテニスのテクニックはまだ、序の口だ。」という場合は、ほんの始まったばかりというだけでなく、未熟で未完成というニュアンスを含みます。語源は相撲の言葉で、すもうを始めたばかりという意味から転じた俗語なので、親しい相手には使えます。
足を踏み入れる
7つ目は、足を踏み入れるです。
意味やニュアンスの違いは以下のとおり。
元のワードに比べると、物事を始めてしばらく経った時にも使える言葉だと思います。人によってはポジティブなワードとは受け取らない人もいると思うので、使う場面には注意が必要です。
物事のはじまり
8つ目は、物事のはじまりです。
意味やニュアンスの違いは以下のとおり。
物事の端緒をひらくこと、物事が生じる最初のことという意味で用いる語で、誰にでもわかりやすい表現なのでおすすめの語。
物事の開始
9つ目は、物事の開始です。
意味やニュアンスの違いは以下のとおり。
物事を始めること、物事が始まることという意味合いの語で、老若男女を問わずわかりやすい表現のため特におすすめ。
物事の幕開き
10個目は、物事の幕開きです。
意味やニュアンスの違いは以下のとおり。
芝居で幕が上がって劇が始まることから転じ、物事が始まることという意味合いの語として使うことができおすすめ。
物事のし始めの横文字・カタカナ英語の言い換え語のおすすめ
最後は横文字・カタカナ英語での言い換え語を紹介します。
こちらはリストのみとなります。
- ファーストステップ
- スタートライン
- ビギニング
- スタート
- オープニング
- バース
- スタートアップ
- ルーツ
- オリジン
- introonsetopeningstarting placeearlier stageearly phase
かっこよく表現したい際、参考にしてください。
まとめ
以上が物事のし始めの言い換え語のおすすめでした。
さまざまな言葉があることがわかりますね。
基本的な意味は同じでも微妙にニュアンスが違ったりもするため、TPOに合わせて言い換え語を使い分けていきましょう。
振り返り用リンク↓
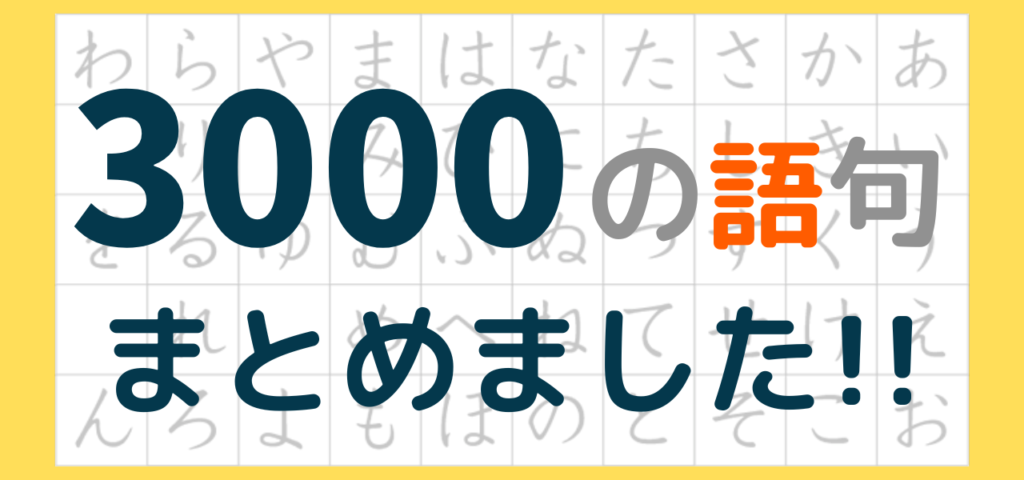
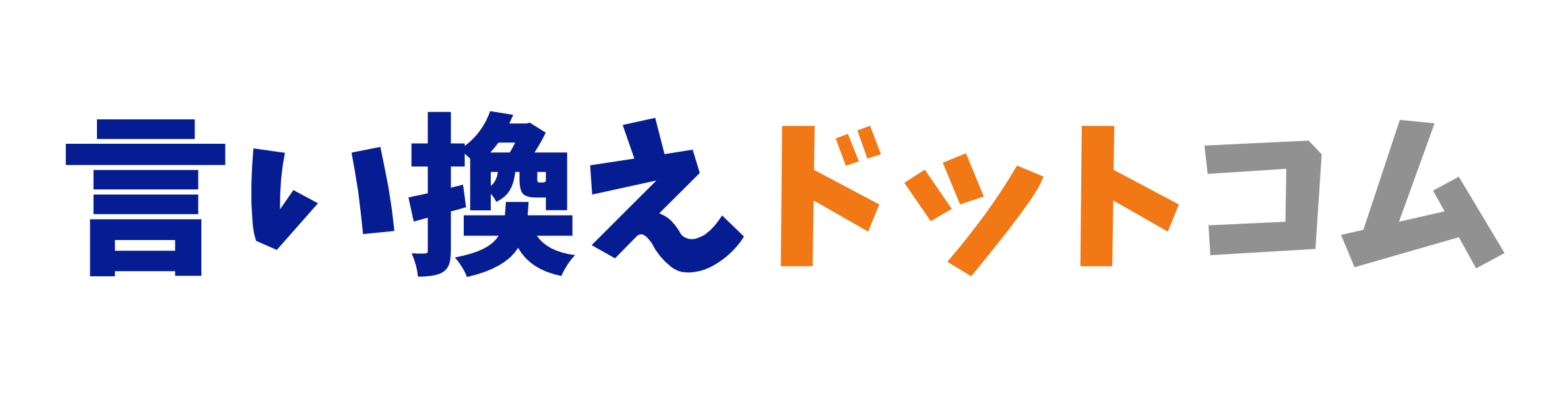

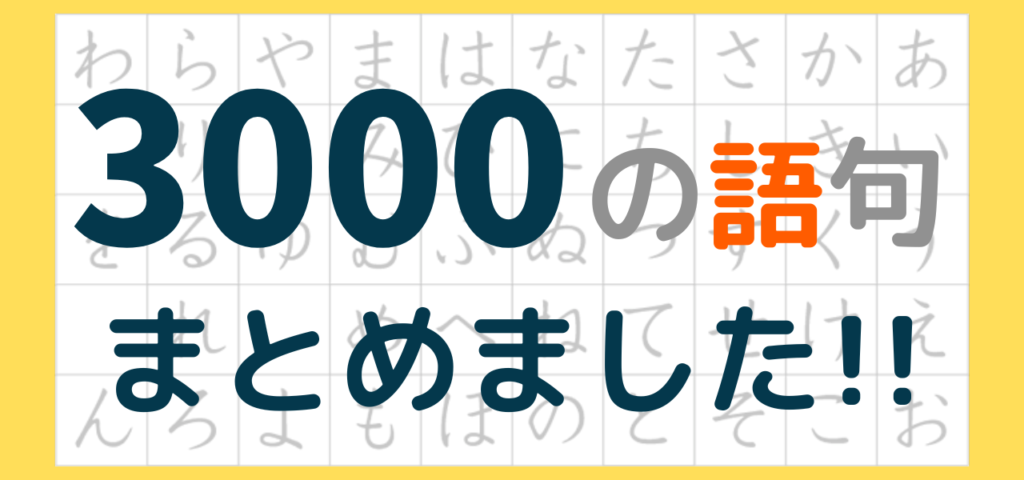
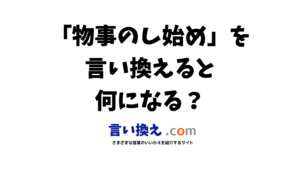
コメント