音頭を取るの言い換え語のおすすめは?ビジネスやカジュアルに使える類義語のまとめ!
本記事では、音頭を取るの言い換え語・同義語(類義語)を解説します。
- ビジネスで使えるきっちりした類語
- 友達同士でカジュアルで使える類語
に分けていくつかのアイデアをまとめました。
また、カタカナ・英語でかっこよく言い換えたい場合のワードもいくつか紹介します。
実際に使われているワードばかりです。ぜひ参考にしてください。
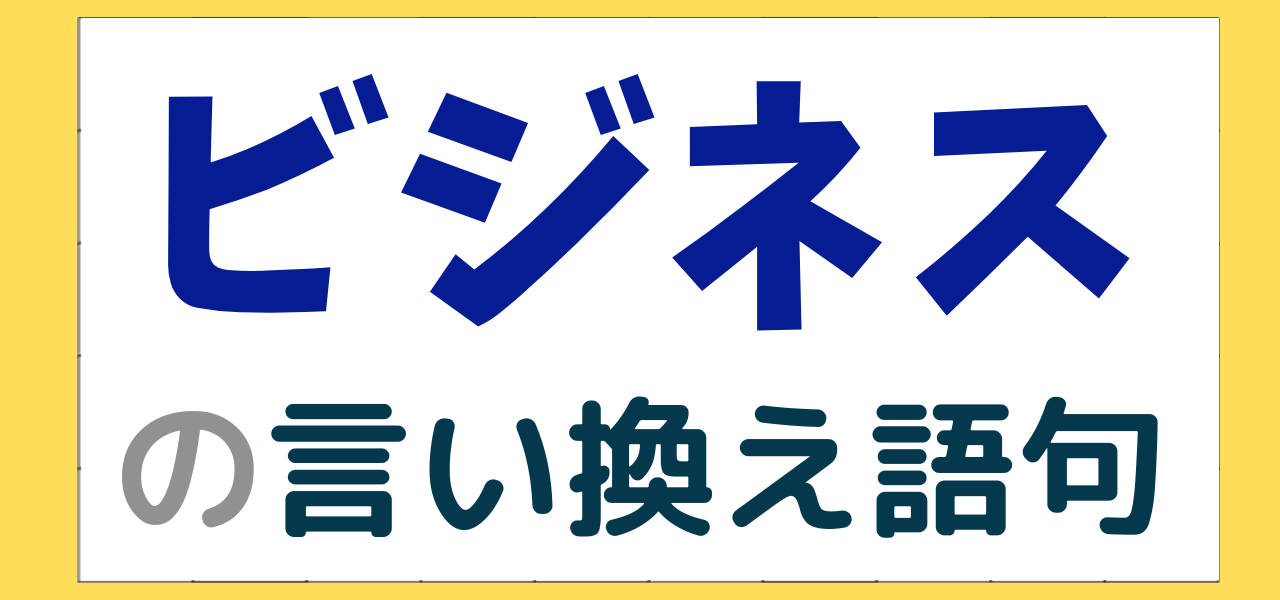 →ビジネスの言い換えを見る | 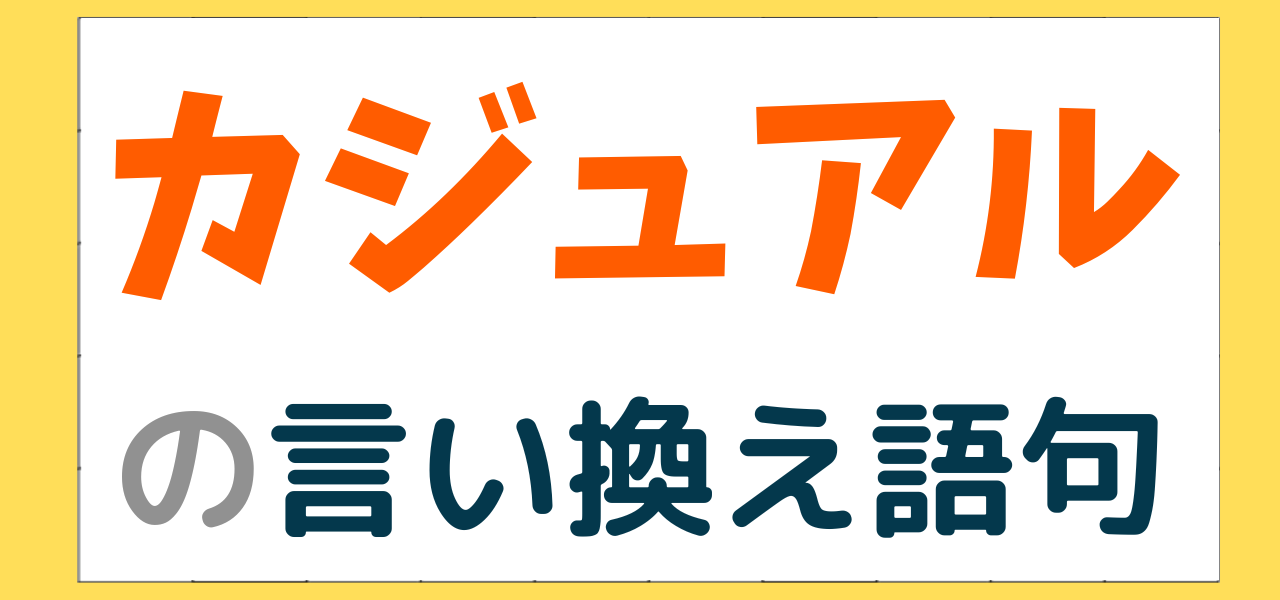 →カジュアルの言い換えを見る | 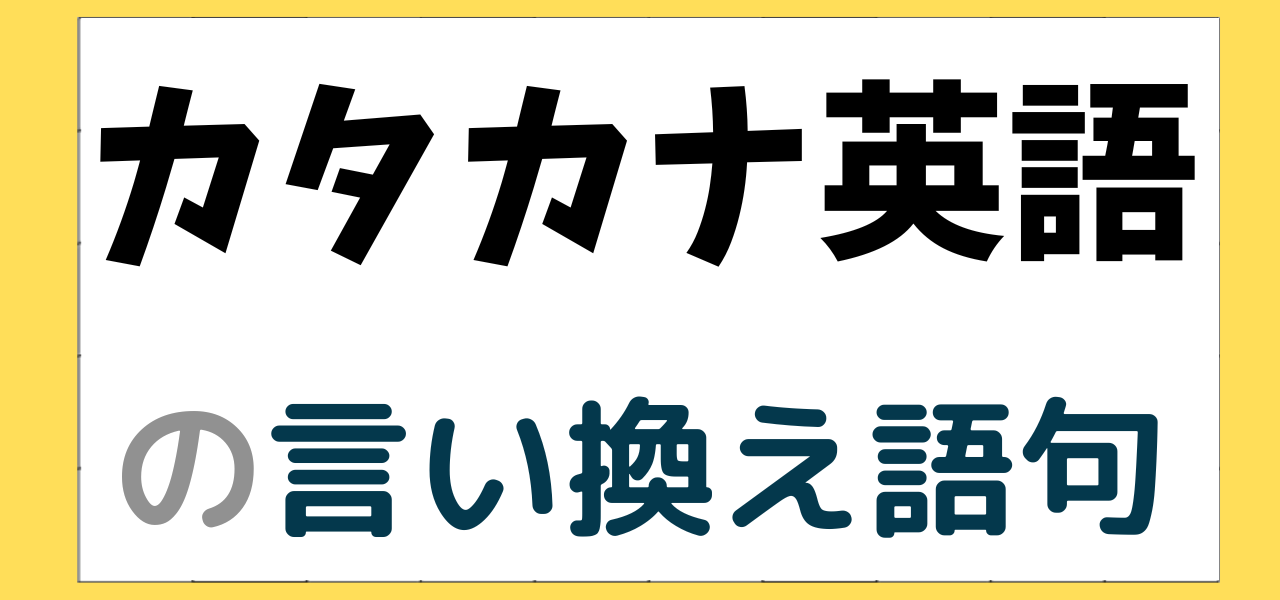 →英語・カタカナの言い換えを見る |
音頭を取るとは? そもそもどんな意味か?
まずは音頭を取るとはどんな意味なのかをおさらいします。
すでに意味をご存知の方は、次の項目まで飛ばしていただき大丈夫です。
意味
まず意味は以下のとおりです。
物事を行う際に皆の先頭に立って統率・牽引すること。
—
集団の先頭で、統率されるようにまとめること
—
イベントやプロジェクトといった、複数人が関わる事の先導・決定を行う役柄を担うという意味です。
意味を全て見る
- ある集団の先頭に立って全体を引っ張ること
- 基本的には先頭に立って準備し、集団をまとめることを指す
- 何らかの物事を、先頭に立って導くという慣用句。
- 合唱の調子を整えるために歌いはじめること、ひょうしをとること
- 先頭に立って物事の計画を練ったり指導したりすること。
- 他の人より先にやること。
例文
つづいて、音頭を取るを用いた例文を紹介します。
昔からの友人である彼が、友人の結婚式の披露宴で乾杯の音頭を取る。
来週の祭りは私の兄が音頭をとり準備がすすめられ、予定通り催される予定だ。
例文を全て見る
- 先月持ち上がった新しい事業企画の音頭を取っていただけますか?
- 彼はまだ若いがしっかりしているので、今年の祭りでは、神輿の列の先頭に立って音頭を取るそうです。
- 今回のプロジェクトでは、注目の成長株が音頭を取ることになりました。
- 今度のプロジェクトでは、以前同様のプロジェクトを成功させた経験のある主任に音頭を取ってもらうことになった。
- 地区会長が音頭を取って、焼失した地元の寺の再建のための寄付を町中で募ることになった。
- 合唱コンクールの練習で調子を合わせるために音頭を取る。
- 今度の歓迎会の音頭を任されることになり、今からとても緊張している。
- 英会話の勉強をするために、私が音頭を取って勉強会を立ち上げた。
注意点(違和感のある、または失礼な使い方)
この言葉を使ううえでの注意点は以下のとおりです。違和感のある使い方にならぬよう注意しましょう。
単なる個人にあたえられる役割ではなく、それを統率する代表者の役割のこと。
—
「今日からプログラミングを勉強するので、計画の音頭を自分で取ることにした。」のように、複数の人が参加しない事柄に対して使われていると違和感を感じます。
—
「彼は祭りを盛り上げるために、神輿の列の最後に付いて音頭を取るそうです」とういう使い方は違和感があります。音頭は集団を導くために先頭に立って取るものだからです。
注意点を全て見る
- やや古めかしい響きがある表現なので、場面によっては別の表現を使うことも検討するとよいでしょう。
- カラオケなどでみんなで歌うときに最初に歌う人にも使うことがあります。時々意味が違うというと勘違いする人もいますが、間違いではありません。
- 文字通り音楽関係の意味があるため、何らかの事業を導くのを明示するなら、対象語に事業を示す言葉を置くべきである。
- 例えば、後で見返すためにビデオで音頭を取る、といった使い方だと全く意味が違ってきます。
- 先頭に立って物事の計画を練ったり指導したりする意味合いがあるが、パーティや歓迎会など大勢が集まり賑やかに過ご場合に使われるニュアンスであり、深刻な会議などで使うのは違和感がある。
- 乾杯の音頭を取る時は、「乾杯の音頭を取らせていただきます」など丁寧な言い回しをするとよい。
ビジネスで使える丁寧な音頭を取るの言い換え語のおすすめ
ビジネスで使えるフォーマルな言い換え語を紹介します。
それぞれ見ていきます。
主導する
まずは、主導するです。
意味やニュアンスの違いは以下のとおり。
リーダーになって導くことを示したフォーマルな表現である。「地元住民が主導して町づくりを進めている」という具合に、進行中の事業の主な責任の所在が誰にあるかを明示する上で重宝しやすい。
旗振り役を務める
2つ目は、旗振り役を務めるです。
意味やニュアンスの違いは以下のとおり。
「旗振り役」は物事の中心にいる人やリーダーというニュアンス。複数の人が集まる企画やイベントの企画や進行を任された時に「旗振り役を務めることになった」という使い方をするのがおすすめ。
先導する
3つ目は、先導するです。
意味やニュアンスの違いは以下のとおり。
「音頭を取る」は若い人にはなじみのない言葉かもしれないので、若い人達がいるときは「先導する」の方がわかりやすいかもしれません。
陣頭指揮に当たる
4つ目は、陣頭指揮に当たるです。
意味やニュアンスの違いは以下のとおり。
元のワードとほぼ同じ意味ですが、プロジェクトの成功を進めるためなど、よりビジネスシーンで使われることが多いです。
先陣を切る
5つ目は、先陣を切るです。
意味やニュアンスの違いは以下のとおり。
元のワードとほぼ同じ意味ですが、よりアグレッシブな印象を与える言葉です。「プレゼンは沖田君に先陣を切ってもらいたい」のように使います。
指揮する
6つ目は、指揮するです。
意味やニュアンスの違いは以下のとおり。
元の語と同義であるが、物事のはじめだけでなく、経過中や終盤までにわたって集団を統制する、声を挙げる意味も含まれる。
リードする
7つ目は、リードするです。
意味やニュアンスの違いは以下のとおり。
意味は元の語とほぼ同義だが、狭い集団だけでなく規模の大きい集団においても使用できる(経済界をリードする、等)。
イニシアチブを取る
8つ目は、イニシアチブを取るです。
意味やニュアンスの違いは以下のとおり。
集団を主導するの意味があり、あるビジネス集団を論理的に導く、のようなニュアンスもあり、ビジネス用語として適しています。
発破をかける
9つ目は、発破をかけるです。
意味やニュアンスの違いは以下のとおり。
「音頭を取る」は雰囲気を高めるという意味にも使えるので、この意味では「発破をかける」が使えます。
音頭を取るのカジュアルな言い換え語のおすすめ
友達同士で使えるようなカジュアルな言い換え語のおすすめを紹介します。
率いる
まずは、率いるです。
意味やニュアンスの違いは以下のとおり。
きわめて汎用性の高い表現であり、日常的な会話文はもちろんのこと、フォーマルな文書やメールで使うのにもおすすめです。
発破をかける
カジュアルの2つ目は、発破をかけるです。
意味やニュアンスの違いは以下のとおり。
同僚達の間で、「来週、業績を回復すべく新社長は社員全員を集めて発破をかけるらしいよ。我々も気を引き締めて出席しないといけないね」などと使うのに適しています。フランクな言い方です。
引っ張る
つづいて、引っ張るです。
意味やニュアンスの違いは以下のとおり。
一番前に立って集団を引っ張るという意味で使えます。「私が引っ張るから(ついてきて)。」のような使い方ができます。
リードする
4つ目は、リードするです。
意味やニュアンスの違いは以下のとおり。
物事を引っ張っていくニュアンスであり、「〇〇がリードして進めていってよ」というような使い方をするのがおすすめ。
トップを切る
5つ目は、トップを切るです。
意味やニュアンスの違いは以下のとおり。
元のワードと意味はほぼ変わりませんが、より平易ないい方でわかりやすくなっているから汎用性が高いです。
楫取り
6つ目は、楫取りです。
意味やニュアンスの違いは以下のとおり。
「グループ研究を効率よく楫取りする。」などといった、物事がうまく運ぶように、誘導・指揮すること。また、その人などの表現に使用することがおすすめです。
牽引する
7つ目は、牽引するです。
意味やニュアンスの違いは以下のとおり。
人の気持を自分の方へ引きよせることや、先頭に立って物事を行うことで他の人や集団を率いる意味もあります。例えば、チームのリーダーとして彼が皆を牽引して頑張っている、といった使い方が出来ます。
仕切る
8つ目は、仕切るです。
意味やニュアンスの違いは以下のとおり。
元の語に比べ物事のはじめだけでなく、経過中や終盤までにわたって集団を統制する、声を挙げる意味も含まれる。
号令をかける
9つ目は、号令をかけるです。
意味やニュアンスの違いは以下のとおり。
同僚達の間で、「来週に、業績を回復すべく新社長は社員全員を集めて新方針に基づく号令をかけるらしいよ」などと使うのに適しています。比較的くだけた表現ですが、論理的なニュアンスもあります。
音頭を取るの横文字・カタカナ英語の言い換え語のおすすめ
最後は横文字・カタカナ英語での言い換え語を紹介します。
こちらはリストのみとなります。
- リード
- イニシアチブ
- lead
- guidance
- initiative
- guide
- induce
- usher
- take the lead
かっこよく表現したい際、参考にしてください。
まとめ
以上が音頭を取るの言い換え語のおすすめでした。
さまざまな言葉があることがわかりますね。
基本的な意味は同じでも微妙にニュアンスが違ったりもするため、TPOに合わせて言い換え語を使い分けていきましょう。
振り返り用リンク↓
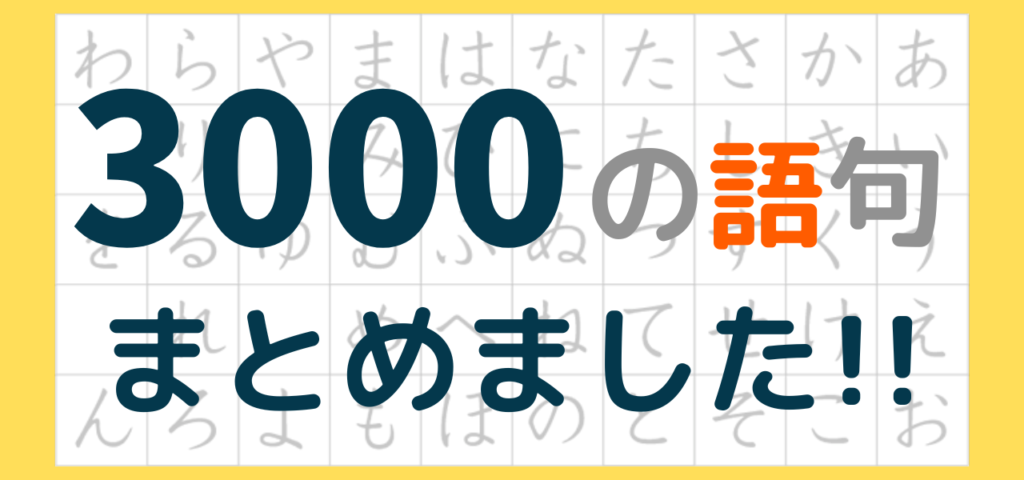
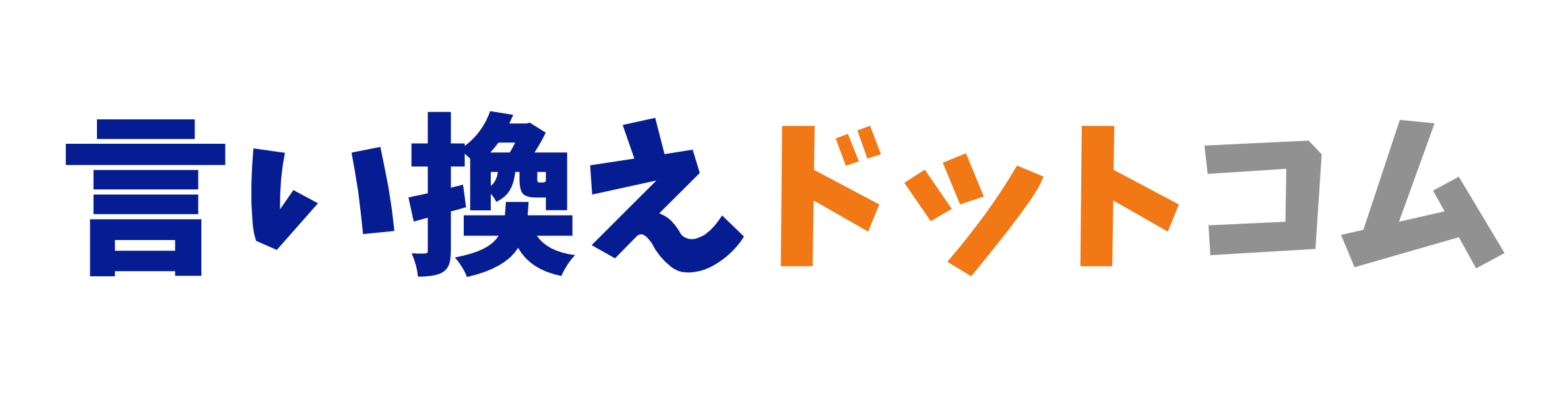

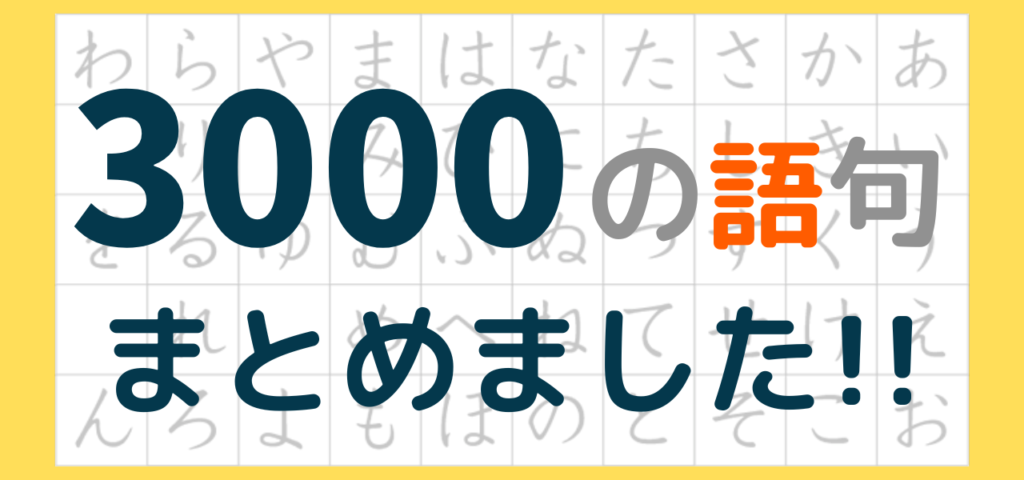
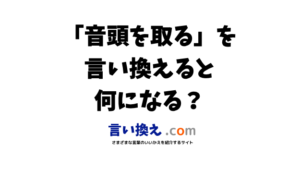
コメント